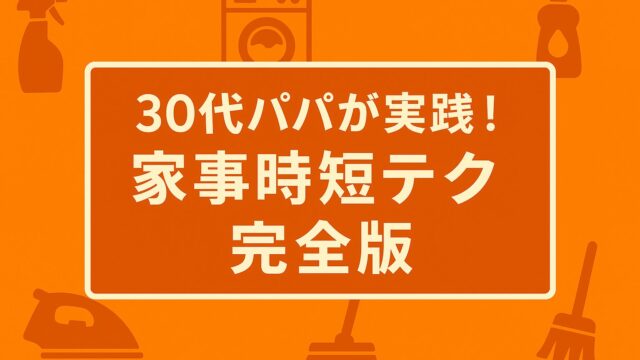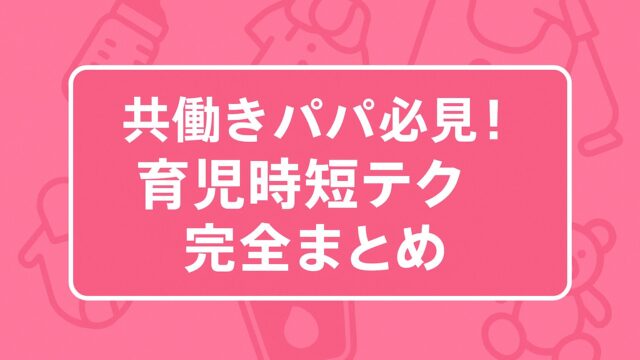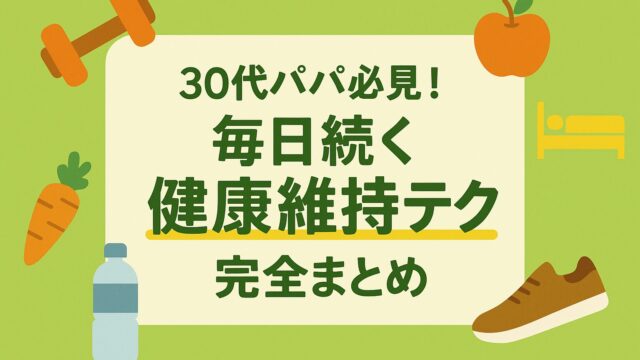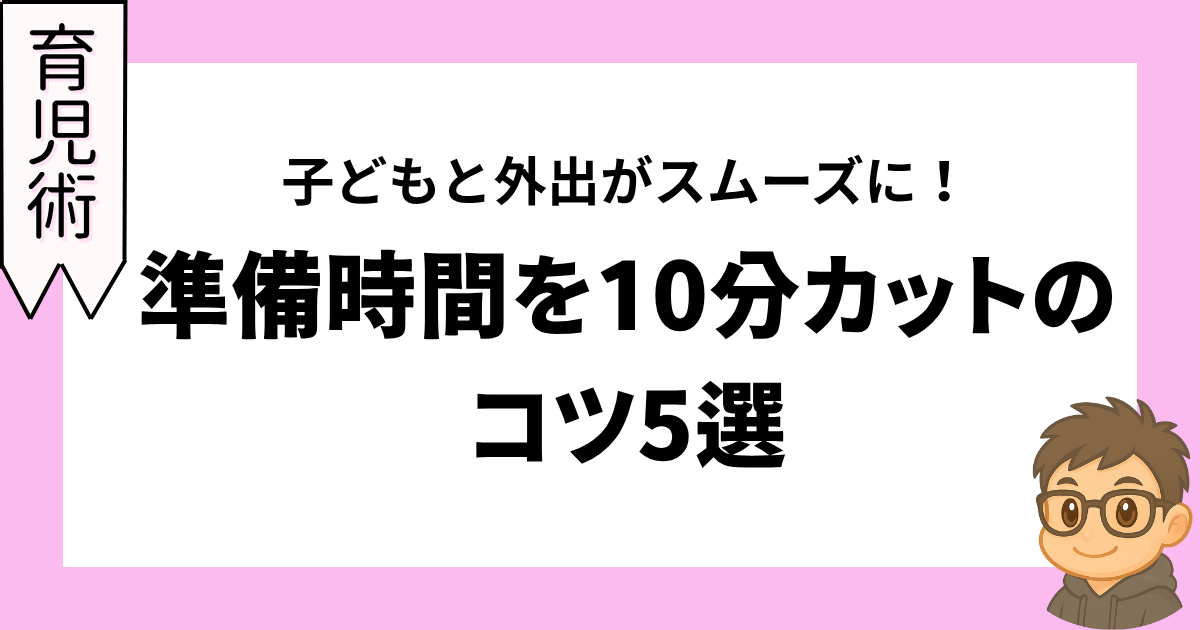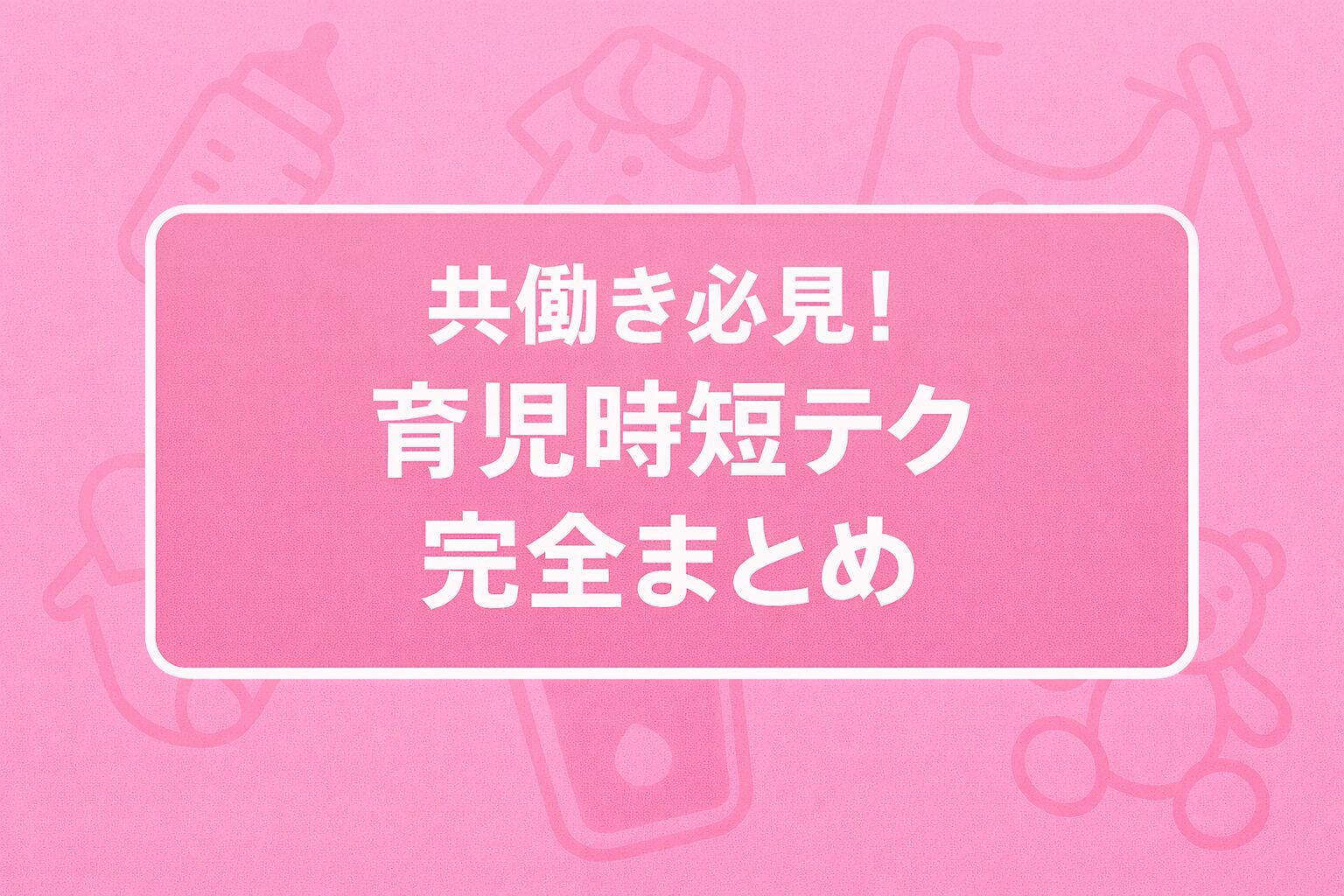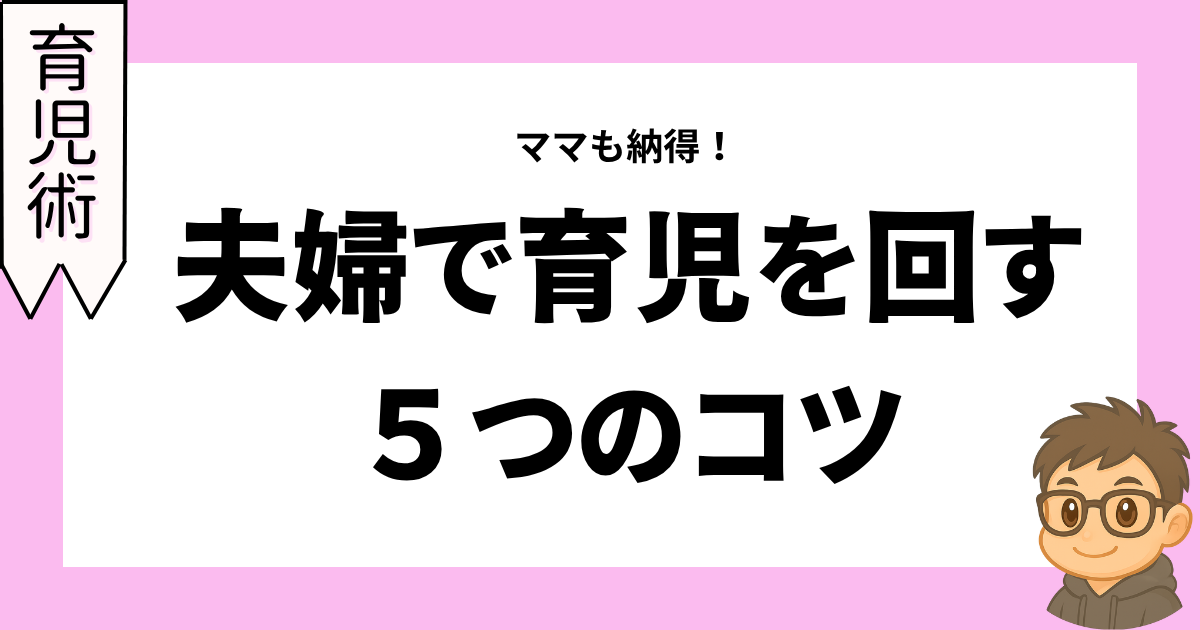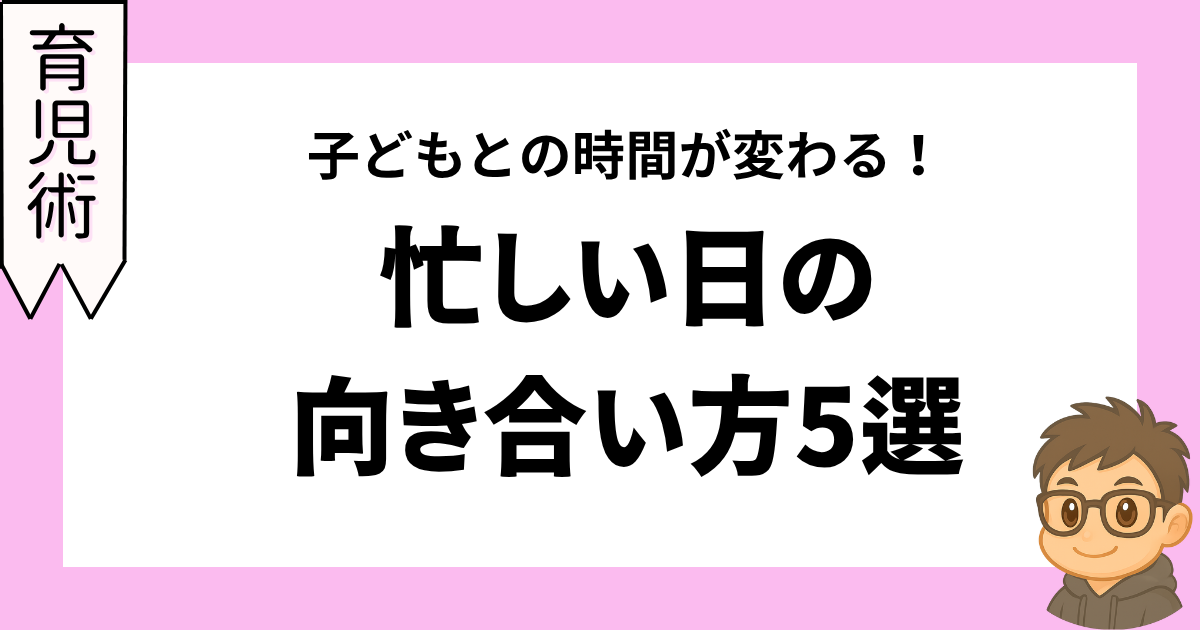忙しいパパでもうまくいく!イヤイヤ期を乗り切る声かけ術5選
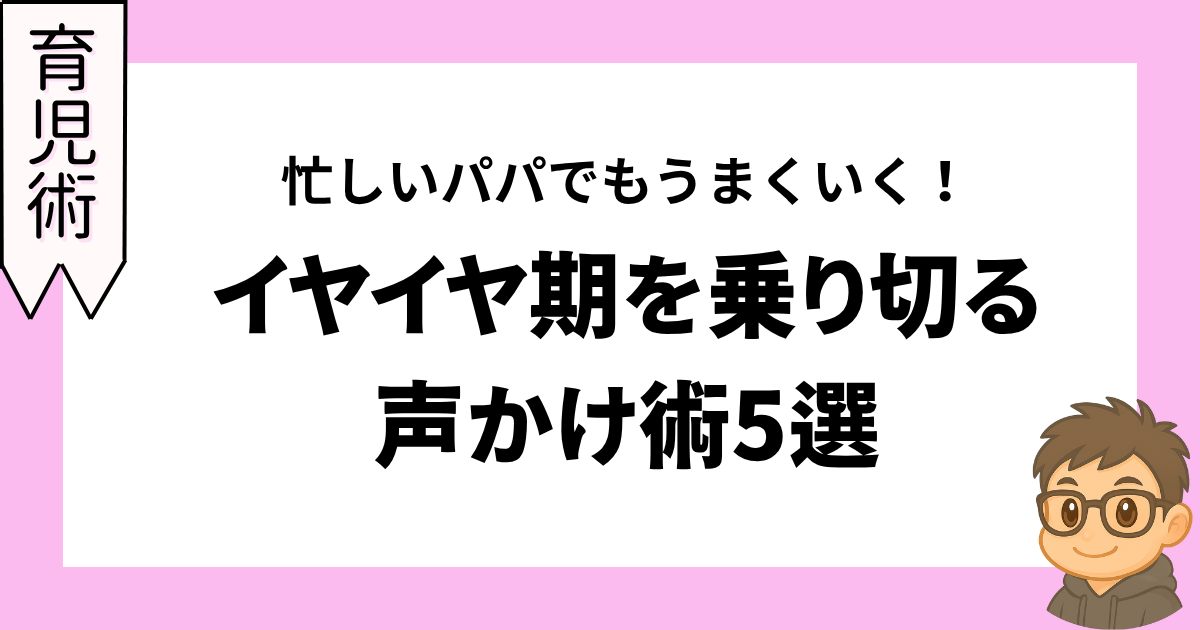
「またイヤイヤが始まった…もう疲れた」
仕事で忙しい毎日、子どもの“イヤイヤ期”に向き合うのは本当に大変ですよね。
ついイライラして、感情的に叱ってしまい、あとから「もう少し上手く言えたら…」と後悔する。
私も同じように悩みながら、どうすれば“うまく付き合えるか”を模索してきました。
そんな中で気づいたのは、少しの言葉の工夫で子どもの反応が変わるということ。
時間も気持ちも余裕がないときほど、「声かけの引き出し」を持つことが支えになります。
この記事では、忙しいパパでも実践しやすい
「イヤイヤ期を乗り切る声かけ術」を5つご紹介します。
読めば、子どもとの関係がぐっとラクになり、
仕事や家事との両立にも少し余裕が生まれますよ。
なぜパパは“イヤイヤ期”で悩むのか?
子どもの成長には必要な“イヤイヤ期”。でも、パパにとっては悩みのタネにもなりがちです。
「イヤ!」と泣き叫ばれたり、何をしても受け入れてもらえなかったり…。
一生懸命やっているのに拒否されると、心が折れそうになりますよね。
とくにパパは、子どもとの接点が限られていたり、
“正解がわからない”中で対応している人も多いです。
私自身、はじめての育児で「この泣き方、どうすればいいの?」と
戸惑うばかりの日々が続いていました。
でもあとから知ったのは、イヤイヤ期は子どもの心が育つ大事なステップだということ。
「自分の思いを伝えたい」「自分で決めたい」という主張の表れなんです。
そう考えると、必要以上に叱るのではなく、
“関わり方”を変えることが大切だと感じました。
✅ 子どもの気持ちに向き合うには、声かけの工夫が効果的
ほんの少し言い回しを変えるだけで、反応がガラッと変わることもあります。
「そうだよね」と共感するひと言を添える
子どもがイヤイヤを爆発させたときこそ、“共感のひと言”が効きます。
大人でも、頭ごなしに否定されるとムッとしますよね。
子どもも同じで、「ダメ!」「やめなさい!」と叱られると反発します。
そこで、「そうだよね」「イヤだったんだね」など、
気持ちを“代弁”してあげるだけで、落ち着くことがあります。
私も、「やりたかったんだよね」と声をかけたことで、
それだけで泣き止んだことが何度もありました。
子どもは“わかってもらえた”と感じると安心します。
この安心が、切り替えのスイッチになるんです。
✅ まずは“受け止める”だけでOK
否定ではなく共感から入ることで、子どもは心を開いてくれます。
指示ではなく“選ばせる”ことで主導権を渡す
「〇〇しなさい」ではなく、子どもに“選ばせる形”にすると、驚くほどスムーズに動いてくれます。
イヤイヤ期の子どもは、自分で決めたい気持ちが強くなります。
そこに一方的な指示がくると、反発心が高まりやすくなります。
たとえば「早く着替えて!」ではなく、
「青い服と赤い服、どっちがいい?」と聞いてみると、
選べることで“自分で決めた”感覚が得られ、行動につながりやすくなります。
うちの子も、「お風呂に入ろう」と言うとイヤがるのに、
「おもちゃ持って入る?それともタオルだけで入る?」と聞くと、
自分で考えて動き始めてくれることが多くなりました。
選択肢を与えることで、親のペースにもっていけるのがコツです。
✅ 「指示」よりも「質問」で切り替える
子どもが“自分で決めた”と思えると、行動がスムーズになります。
「あとでね」をやめて、時間で約束する
“あいまいな言い方”よりも、具体的な時間の約束が子どもには伝わりやすくなります。
「あとでね」「もうちょっと待って」――
大人には便利な言葉でも、子どもにとっては不安とストレスのもとになります。
時間の感覚がまだ未発達な時期だからこそ、
“いつなのか”がわからないまま待たされるのはつらいのです。
たとえば、「あとでおやつね」ではなく、
「このテレビが終わったら食べようね」など、
目に見える“区切り”で伝えると納得しやすくなります。
私も、「あとで遊ぼう」は毎回ぐずられていましたが、
「ごはん食べて、お皿片付けたら遊ぼうね」と伝えるようにすると、
スムーズに切り替えられるようになりました。
✅ “見通し”を与えると、子どもは落ち着く
あいまいな言葉を避けて、具体的な“タイミング”を伝えてあげましょう。
大人の都合ではなく、気持ちを説明する
「ダメ!」ではなく、“なぜダメなのか”を子ども目線で説明すると納得してくれやすくなります。
「今はムリ」「静かにして」など、大人の都合だけを押しつけると、
子どもは理不尽さを感じて、より反発してしまいます。
そこでおすすめなのが、“理由+気持ち”で伝える方法です。
たとえば「お菓子はダメ!」ではなく、
「今食べるとごはんが食べられなくて、おなか痛くなるかも」
「ママが困っちゃうんだよ」といった、やさしい言葉で理由を添えるだけで反応が変わります。
私も、「やめて」と言う代わりに「パパはちょっと疲れちゃったな」などと、
自分の気持ちを伝えるようにしただけで、空気がやわらかくなりました。
子どもは小さくても、“ちゃんと伝えれば理解しようとする力”を持っています。
✅ ルールよりも“気持ち”が届く
大人の事情を押しつけるのではなく、「どうして?」に答える姿勢が大切です。
5. 感情が爆発したら“安全な場所”を作る
泣いたり怒ったりしているときは、“落ち着ける場所”があるだけで子どもは安心します。
イヤイヤ期の子どもは、自分でも感情のコントロールがうまくできません。
「泣かないの!」と言われても、止められないのが本音です。
そこで、あらかじめ“落ち着けるスペース”を用意しておくと役立ちます。
たとえばお気に入りのぬいぐるみがある場所、
静かにできるクッションやマットの上などです。
うちでは、子どもと一緒に「ここは休憩コーナーね」と決めておくことで、
「イライラしたらここでひと休み」という流れが自然とできました。
逃げ場所があるだけで、子どもも「気持ちが乱れても大丈夫」と思えるんです。
✅ 泣いても怒っても、安心できる場所を
感情を落ち着けるスペースがあると、子どもの“自己調整力”が育ちます。
まとめ:「ちゃんと向き合う姿勢」が伝われば大丈夫
イヤイヤ期は、子どもが“自分”を確立し始める大事な時期。
そのぶん、親にとっては試されているように感じる瞬間もありますよね。
でも、少しだけ言葉を工夫するだけで、子どもの反応は大きく変わります。
今回ご紹介した声かけ術5つは、どれも「子どもの気持ちを尊重する」ものばかり。
感情的になる前に、“伝え方”を見直すだけで心が通じやすくなるんです。
毎日完璧にできなくても、向き合おうとする姿勢はきっと伝わります。
ぜひ、今日から1つだけでも取り入れてみてください。
【つまずきやすい場面をラクに】
✅ 忙しい日の向き合い方5選
✅ 寝かしつけ時短法5選
✅ 育児時短テク完全まとめ
👉 家事時短の工夫で余裕をつくる