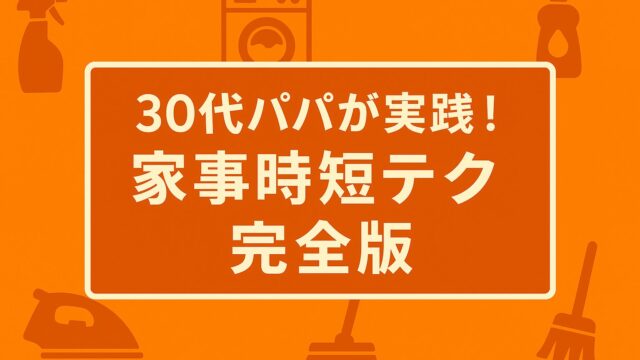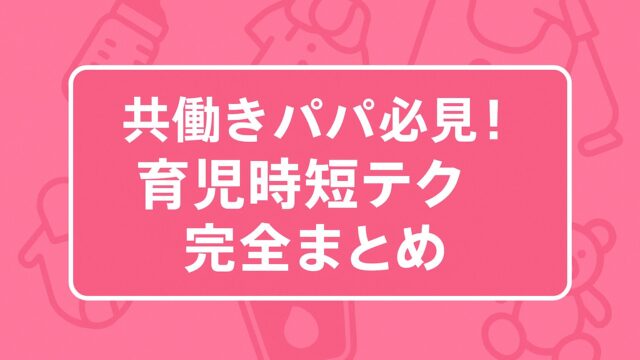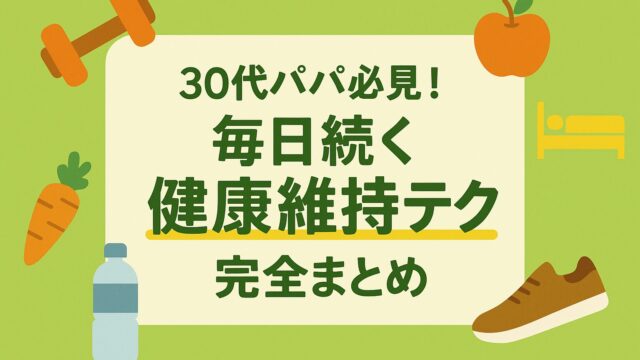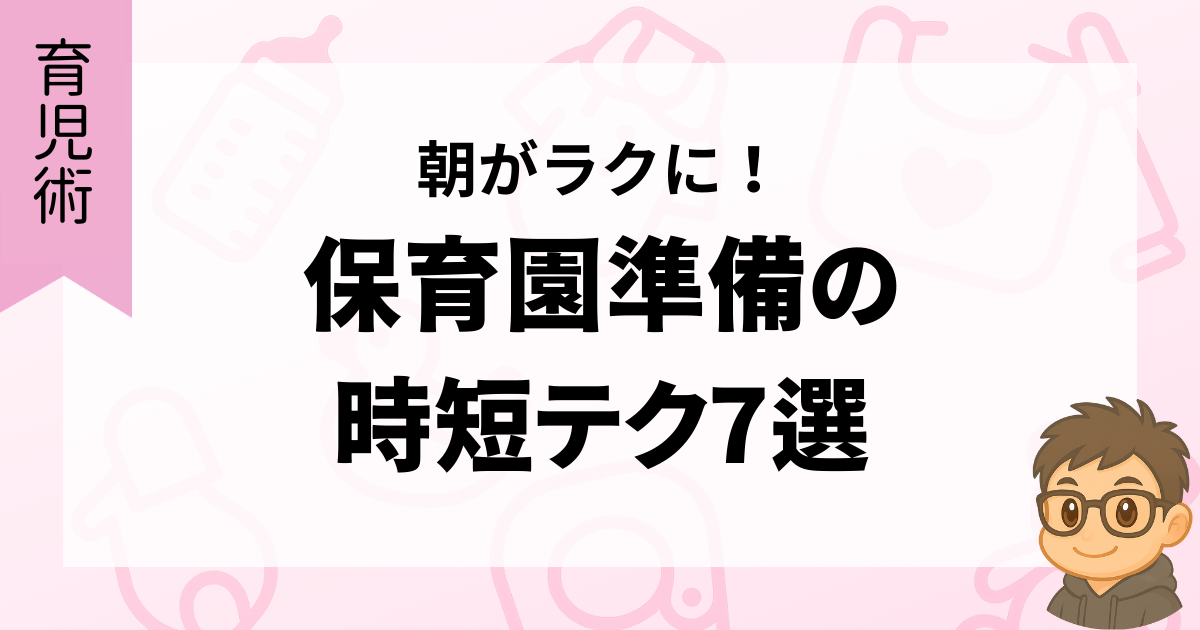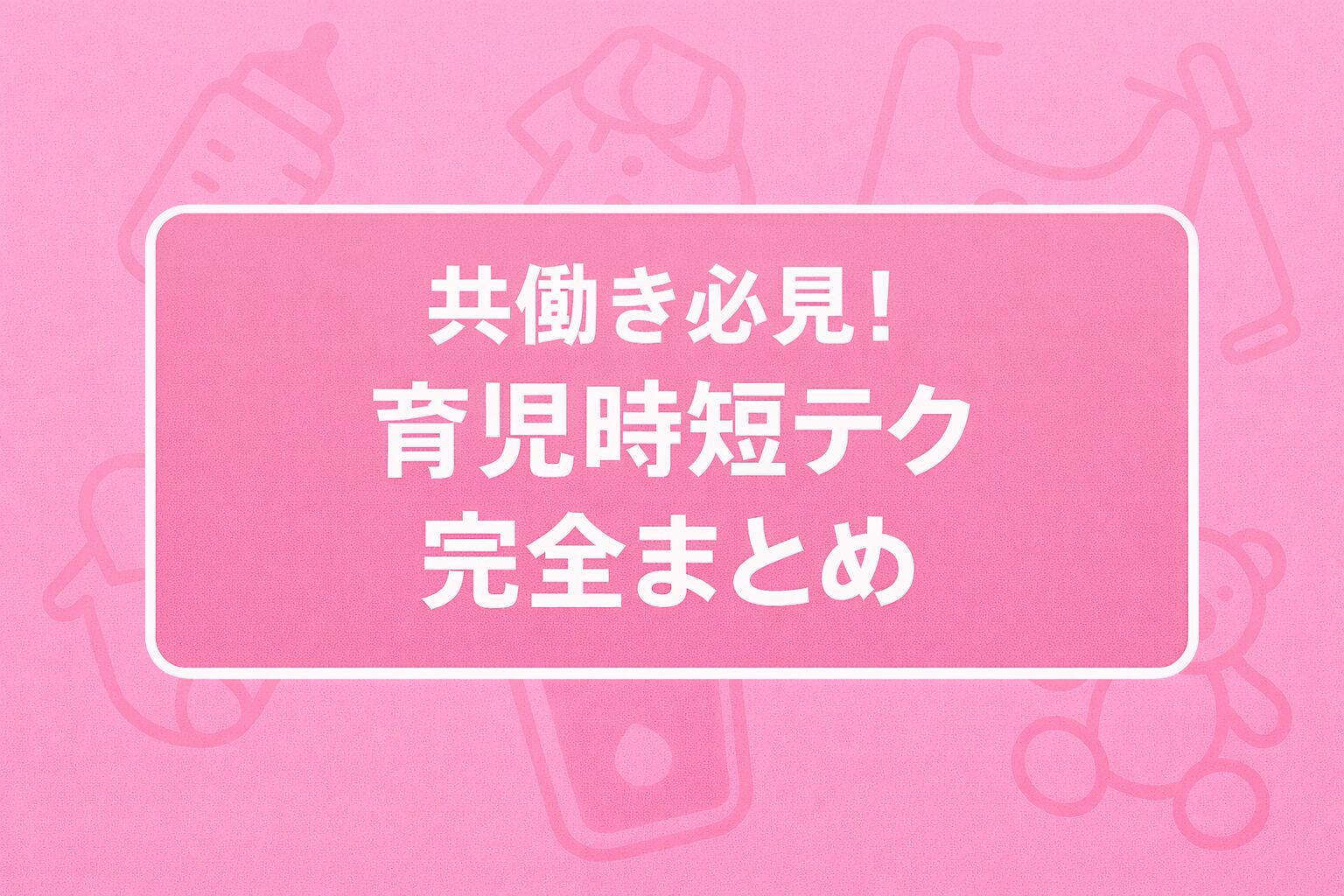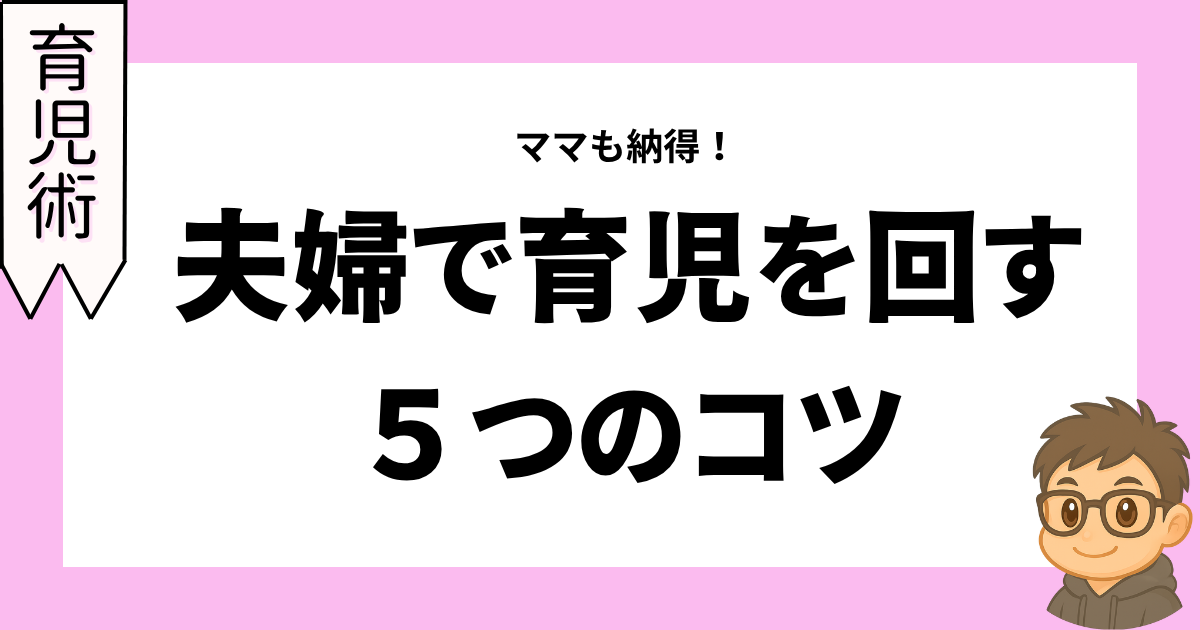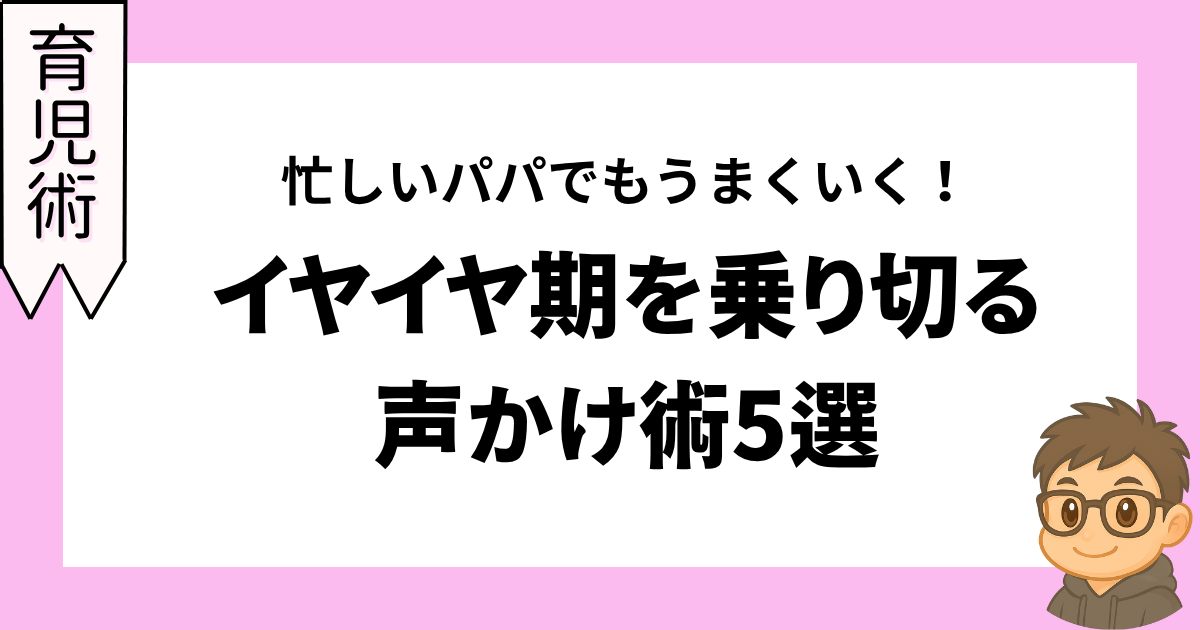“できた!”が増える!パパと始める7つの家しごと

朝の支度や片づけで、ついイライラしてしまうことありませんか?
「なんで何度言ってもやらないの…」そんな気持ち、パパなら一度は経験しているはずです。
でも、毎日「早く!」「片づけて!」と怒るのは疲れるし、子どもにとってもストレス。
やらないんじゃなくて、“やれるきっかけ”がないだけかもしれません。
実はうちでも、子どもがまったく動かず困っていましたが、
お手伝いを通して“できた!”を積み重ねたことで、自然と自分から動けるようになりました。
この記事では、3〜6歳の子でもできる「簡単なお手伝い7選」を紹介します。
パパと一緒に始めれば、子どもの自立心を育てながら、家事も少しラクになりますよ。
大事なのは、「完璧にやらせること」ではなく、“できた!”という達成感を与えること。
その繰り返しが、自分で考えて動ける子どもを育ててくれます。
「自分で動く子」を育てるには?
自立は「経験の積み重ね」で育つ
子どもが自分から動かないのは、やる気がないからではありません。
「何をすればいいか分からない」「やっていいか分からない」という不安があるだけなんです。
だからこそ、自分でやってみる機会を増やすことが大切。
たとえば、「これお願いできる?」と声をかけて“自分ができた”という経験を少しずつ積ませてあげることが、自立への第一歩になります。
✅ 小さな成功体験が、自分から動く力になる
「やってみた→できた→褒められた」の流れを何度も繰り返すことで、
子どもは「自分でやりたい」と思うようになります。
お手伝いで「役割感」と「成功体験」を与える
子どもにとって、家族の一員として役に立てたという感覚はとても大きなもの。
「○○ちゃんがやってくれて助かったよ」と伝えるだけで、“自分も役に立てる”という自信が生まれます。
お手伝いは、その小さな成功を日常で体験できる絶好のチャンス。
完璧でなくてもいいので、まずは簡単で「ありがとう」が言いやすいことからスタートしてみましょう。
✅ 役に立てた実感が、自立の芽になる
手伝いを通じて「自分もできる」と思える子は、
自分から行動する力が少しずつ育っていきます。
今日から始める!パパとやる7つの家しごと
① テーブルを拭く/食事の前後を手伝う
一番取りかかりやすいお手伝いが「テーブル拭き」や食事の準備。
子どもにとってもわかりやすく、「目に見える成果」があるので、達成感を感じやすい作業です。
「お皿を並べる」「拭いたらピカピカになる」など、すぐに結果が出ることがポイント。
特に3〜5歳くらいの子どもは、目の前で変化がある作業にやりがいを感じやすいです。
最初は雑でもOK。パパが「ありがとう!助かったよ」と伝えれば、それだけでモチベーションアップ。
「お兄ちゃんになったね」などの声かけも、誇らしさを育てる良いきっかけになります。
✅ “すぐに結果が見える作業”が第一歩にぴったり
テーブルを拭くだけでも、「自分の仕事」として認識しやすい。
目に見える変化と達成感で、子どものやる気が自然と芽生えます。
② 靴をそろえる/玄関まわりを整える
玄関の靴をそろえるのは、子どもでもすぐにできて「生活のマナー」も学べるお手伝い。
外から帰ったら靴をそろえる、出かける前に玄関を整える。この小さな習慣が、整理整頓の基本になります。
ポイントは、パパも一緒にやってみせること。
「パパもそろえるから○○もお願いね」と声をかけると、子どもは真似をしながら自然と覚えていきます。
また、「今日はきれいに並んでるね!」「靴がそろってると気持ちいいね」など、
気づいたらすぐに声をかけることで“気持ちよさ”の実感も伝わります。
✅ “整える気持ちよさ”がわかると習慣になる
靴そろえは、小さな達成感と生活マナーを同時に学べるお手伝い。
「見てくれてる」と感じることで、子どもは進んでやりたくなります。
③ 洗濯物をカゴに入れる・干す手伝い
洗濯は「準備→作業→片づけ」がセットになった“工程のあるお手伝い”。
だからこそ、「できた感」や「役に立っている感覚」が強くなります。
まずは洗濯物を脱いだらカゴに入れるところから始めましょう。
慣れてきたら、タオルや靴下を干す・取り込むなど簡単なパートだけを任せても◎
洗濯バサミを使って干す作業は、手先を使う練習にもなります。
「パパと競争してみる?」など、ゲーム感覚で取り入れると楽しく習慣化できます。
✅ 洗濯は“達成感+生活力”が育つお手伝い
家の中での「流れ作業」に関われることは、子どもにとって新鮮。
親が楽しんで一緒にやることで、続けたくなる行動に変わります。
④ おもちゃを片づける習慣づくり
片づけは“やらされる”と面倒に感じやすいけれど、“ルール化”すれば自然とできるようになります。
とくにおもちゃの片づけは、「遊びの終わり」を子どもに意識させるチャンスです。
おすすめは、“場所とタイミング”を決めること。
たとえば「ごはんの前におもちゃをおうちに戻そうね」など、片づける時間を習慣に組み込むと、自然に続きやすくなります。
また、収納を子どもが届く高さにしたり、種類ごとにラベルを貼るなど、仕組みを整えることも大切です。
「おもちゃもおうちに帰るんだよ」という声かけで、親しみもわきやすくなります。
✅ 「片づけること=当たり前」にする仕組みを
ルールや時間を決めることで、“やらなきゃ”から“毎日のこと”へ。
仕組みと声かけで、子どもの片づけ力が自然に育ちます。
⑤ 服をたたむ・引き出しにしまう
服をたたむ作業は、手先の動きと“整理する感覚”を育てるのにぴったりなお手伝い。
たたみ方に決まりがあることで、「きれいにやってみよう」という意識も自然と生まれます。
最初はタオルや靴下など、サイズが小さくて簡単なものから始めるのがおすすめ。
うまくできなくても、「丁寧にたたもうとしてくれたね」と過程をしっかり認めてあげましょう。
しまう場所もラベリングするなどして、子ども自身がどこに片づけるか判断できるようにすると、
「自分で最後までできた!」という達成感が生まれます。
✅ “片づけまで任せる”ことで責任感が育つ
服をたたむだけでなく、しまうまでやってもらうと一連の流れが身につきます。
自分の持ち物を管理する習慣が、自然と自立心につながります。
⑥ ゴミを拾う/ティッシュを捨てる
“出したものを元に戻す”という意識を育てるには、ゴミを捨てる習慣が効果的。
ティッシュやお菓子の袋など、目に見えるゴミは子どもでも処理しやすい身近なタスクです。
「これ、ゴミ箱にポイってお願いしていい?」と簡単なお願いから始めるのがコツ。
その都度「ありがとう!お部屋がきれいになったね」と声をかければ、達成感につながります。
また、「使ったら片づける」「汚れたらふく」という習慣にもつながっていくので、
生活全体の“気づく力”や“自分ごと感”を育てる第一歩になります。
✅ “小さなゴミ捨て”が思いやりのスタートになる
家の中をきれいに保つ行動は、自分だけでなく家族のことを考える力につながります。
パパの声かけが、その意識を自然に育ててくれます。
⑦ 朝の支度チェック/持ち物をそろえる
朝の準備を“自分で確認する”習慣がつくと、1日のスタートがスムーズになります。
とくに保育園や幼稚園の準備は、毎日同じ流れなのでルール化しやすいです。
「お弁当持った?」「ハンカチ入れた?」とパパが毎回聞くのではなく、
“子ども自身がチェックする仕組み”を作ることがカギ。
たとえば、「準備リスト」を作ってシールでチェックできるようにすると、楽しみながら習慣になります。
最初は一緒に確認しながら、「○○は自分でできたね!」と声をかけましょう。
“できた”体験の積み重ねが、自信と自立につながります。
✅ “自分で確認できる仕組み”が自立の土台になる
パパが手を出しすぎず、サポート役にまわるのがポイント。
子どもの「できる」を引き出すことで、毎朝の支度がぐっとラクになります。
まとめ|“やらせる”じゃなく“一緒にやる”から始めよう
子どもに家のことを手伝ってもらうとき、
つい「ちゃんとやってほしい」「しっかりやらせたい」と思ってしまいますよね。
でも、最初の一歩で大切なのは“できばえ”ではなく“関わること”そのもの。
パパが楽しそうに家しごとをする姿や、「ありがとう」の一言が、
子どもにとって最高のモチベーションになります。
「今日からこの1つだけ一緒にやってみよう」
そんな気軽なスタートが、子どもの自信と家族の時間を少しずつ育ててくれます。
「これならできそう」と思った1つを、今日の夜に試してみてください。
家事は“家族のチームプレイ”。
小さな積み重ねが、親子の関係も暮らしもラクにしてくれますよ。
【一緒に進める家事のコツ】
✅ 見守り知育おもちゃ5選
✅ 夫婦で育児を回すコツ5つ
✅ 育児時短テク完全まとめ
👉 家事全体の時短術はこちら