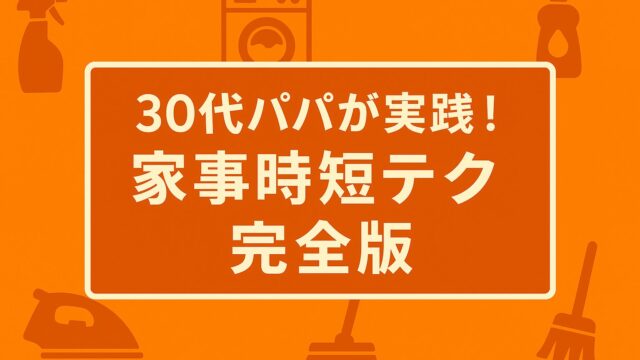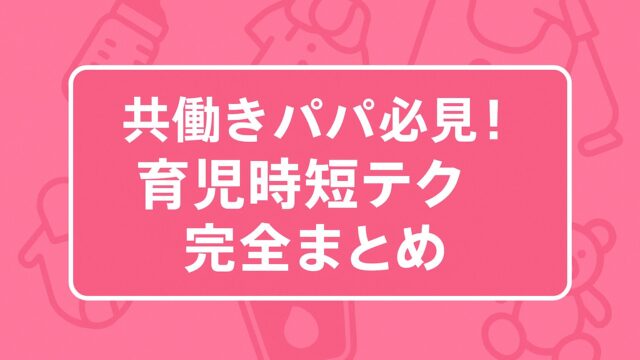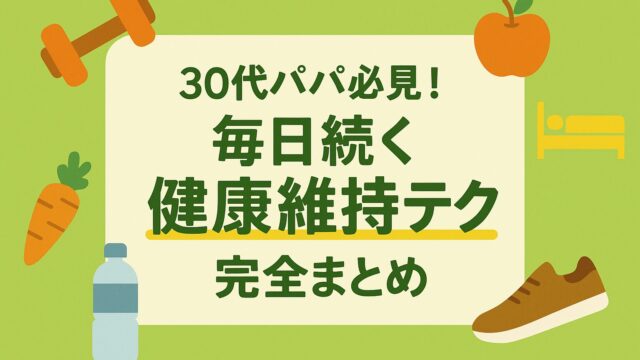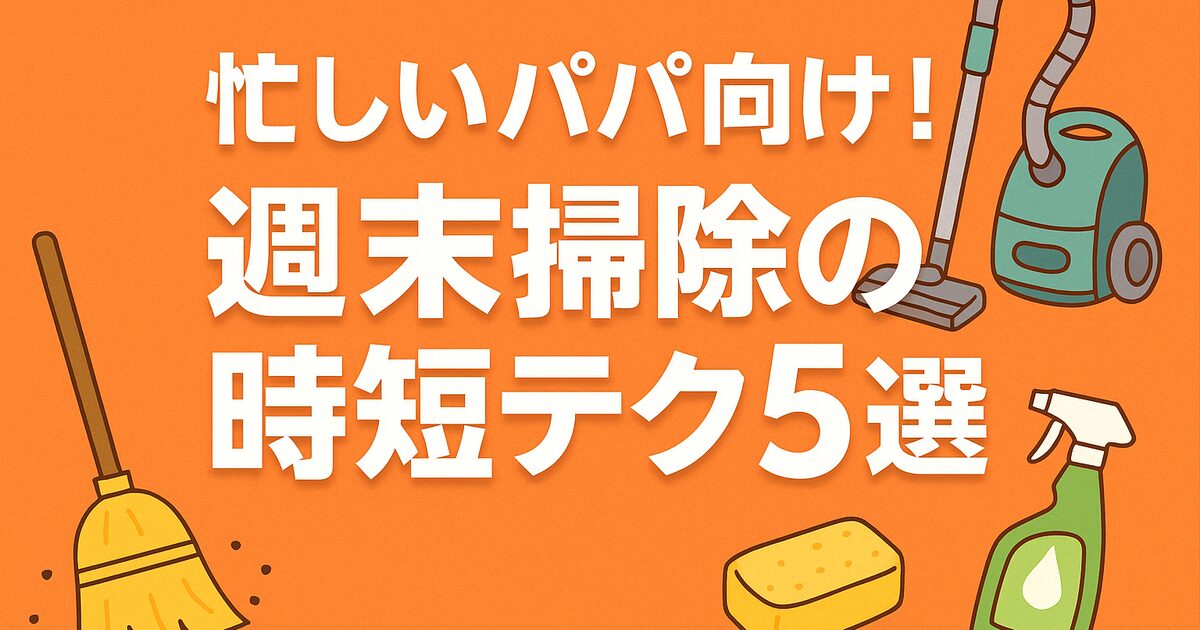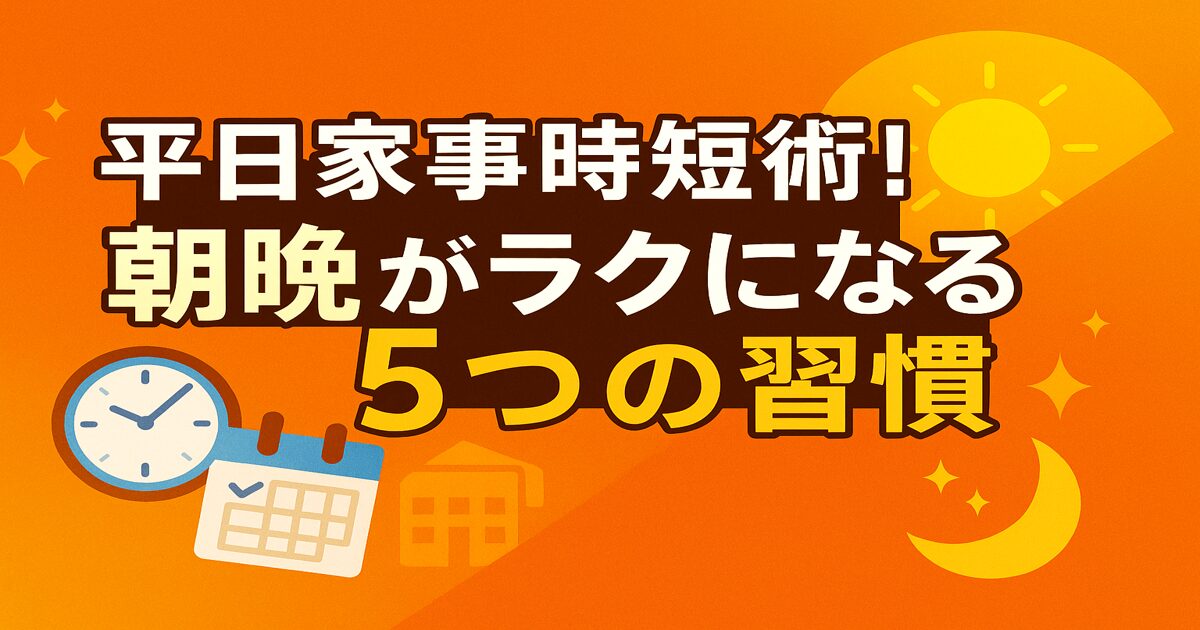共働きパパ必見!子どもとできる家事5選

毎日の家事、仕事、育児でバタバタ。
「子どもがいて、家事が思うように進まない…」
そんなふうに感じること、ありませんか?
やることは多いのに、時間はどんどん過ぎていく。
寝かしつけたあとはクタクタで、何もできない日も。
「もっとラクに家事ができたらな…」と、つい思ってしまいますよね。
私も共働き家庭で2人の子どもを育てています。
家事も育児も仕事もやることが多すぎて、とにかく時間が足りない毎日でした。
でも、「子どもと一緒にやる家事」を取り入れてから、気持ちにも時間にも余裕ができました。
この記事では、子どもと一緒にできる簡単な家事を5つ紹介します。
特別な道具や広い家は必要ありません。今日からすぐ試せる内容です。
読むことで、「家事=負担」ではなく「家事=家族の時間」になるヒントが見つかります。
そして、少しの余裕が「自分の時間」や「副業時間」にもつながっていきます。
家族の時間も、自分の時間も大事にしたい。
そんな共働きパパにこそ読んでほしい記事です。
忙しい家庭にこそ「子ども家事」が効果的な理由
家事がスムーズになる
子どもと一緒に家事をすることで、家事の流れがスムーズになります。
子どもが簡単な作業を手伝ってくれると、親の作業も中断せずに進められます。
結果的に、家事にかかる時間が減り、他のことに使える余裕が生まれます。
たとえば、洗濯物の仕分けやタオルたたみなどは子どもにもできる作業です。
親が料理中に子どもが「タオルたたみ」をしてくれれば、並行して家事が進みます。
「少しの手伝い」が積み重なると、大きな時短効果になります。
子どもが自立しやすくなる
家事は子どもにとっての“学び”にもなります。
日常の中で家事を経験することで、「自分でできること」が自然と増えていきます。
共働き家庭では、親が忙しくても子どもが少しずつ自立していれば大きな助けになります。
「お箸を並べる」「ゴミをまとめる」などの小さな行動でも、成功体験になります。
子どもは“できた”という自信から、他のことにも意欲的になります。
親子のコミュニケーションが増える
一緒に家事をする時間は、親子の会話のきっかけにもなります。
忙しい毎日でも、自然と顔を合わせて話せる時間ができるのは大きなメリットです。
特に小さい子どもは、「遊び」と「家事」の境目があいまいです。
雑巾がけを競争ゲームにしたり、洗濯物の色分けをクイズにしたり。
楽しさを加えることで、親子のやり取りも活発になります。
子どもと家事をすることで、家庭全体がラクに、明るくなります。
親も子どもも嬉しい“いいサイクル”が生まれます。
子どもと一緒にできる!簡単家事アイデア5選
1. 洗濯物を一緒にたたむ・仕分けする
洗濯物は子どもと一緒に取り組みやすい家事のひとつです。
たたむ作業や靴下のペアを見つける仕分けは、遊び感覚でできる内容です。
洗濯物を一緒にたたむことで、「人のものを大切に扱う」という感覚も育ちます。
また、親が他の家事をしている間に子どもが分担できれば、時短にもつながります。
例えば、「パパの靴下を見つけてね!」と声をかければ、
子どもはゲーム感覚で取り組みやすくなります。
自然と集中力や分類する力も養われます。
2. 食前のお箸並べ・食後の食器運びを任せてみる
食事の準備や片付けは、子どもにとって取り組みやすい家事です。
とくにお箸やコップなど、軽くて扱いやすいものなら安心して任せられます。
「お箸を人数分並べてみよう」「食器をシンクまで運んでくれる?」など、
声かけひとつで立派なお手伝いに早変わりします。
子どもが“家族の一員として役に立てた”という満足感を得られる機会にもなります。
習慣化すれば、家事の一部が自然と分担され、親の作業がスムーズになります。
3. 掃除グッズを使った“遊び掃除”
掃除は、子どもが「体を動かしながらできる家事」として最適です。
遊び感覚を取り入れれば、楽しく続ける習慣にもなります。
クイックルワイパーやハンディモップは子どもでも扱いやすい道具です。
「このへんをピカピカにできるかな?」と声をかければ、
“お掃除ごっこ”のように楽しんでくれます。
床のほこり取りや棚の拭き掃除など、手が届きやすい場所から始めるのがコツです。
「掃除=楽しいこと」と感じられれば、日常的に関わりやすくなります。
4. おもちゃや本の片づけをルール化
片づけは、子どもの「自分でやる力」を育てる家事の第一歩です。
遊びっぱなしを防ぐためにも、“ルール化”が効果的です。
「おもちゃは箱に戻す」「絵本は棚に立てる」など、
動作をシンプルにしておくと、子どもも迷わず行動できます。
写真付きラベルや色分け収納にしておくと、より分かりやすくなります。
「片づけはごはん前にする」など、タイミングも決めておくと習慣化しやすくなります。
5. 一緒にお買い物・食材の仕分けを体験
買い物や食材の片づけも、子どもと一緒にできる立派な家事です。
日常の流れを見せながら、生活の仕組みを自然と教えられるチャンスにもなります。
スーパーでは「バナナを1房選んで」「かごに牛乳を入れてね」など、
簡単な役割を渡せば、子どもも主体的に動いてくれます。
帰宅後も「冷蔵庫はここ」「おやつはこの箱」など、決まった場所に片づける習慣が身につきます。
“やらせてみる”ことで、物の扱いや順番を自然に学べます。
楽しく続けるための3つのコツと注意点
1. やりすぎない・求めすぎない
子どもと家事をするうえで大切なのは「完璧を求めない」ことです。
最初からうまくできなくてもOK。失敗も含めて“経験”として受け止めましょう。
「もっとちゃんとやって」「それじゃダメ」などと言ってしまうと、
子どもは“怒られた記憶”の方が強く残ってしまいます。
結果として、お手伝い自体を嫌がるようになってしまうこともあります。
たとえばタオルのたたみ方がバラバラでも、
「ありがとう!助かったよ」と伝えることで“できた喜び”が生まれます。
2. 「できた!」をしっかり褒める
子どもは「認められることで伸びる」生きものです。
小さなことでも、やり遂げたらしっかり褒めましょう。
「ありがとう」「すごいね」「またお願いね」などの言葉が、
次もやってみようという意欲につながります。
“誰かの役に立てた”という感覚は、子どもの自己肯定感を高めます。
たとえば、お箸を人数分そろえられたときに「完璧だね!」と一言添えるだけで、
子どもは嬉しくなって笑顔になります。
3. 短時間でも“習慣”にすることが大切
家事は“習慣化”することで無理なく続けられます。
忙しい日でも、5分だけ取り組むだけで十分効果があります。
一度にたくさんやろうとすると、親も子どもも疲れてしまいます。
「毎日少しずつ」がポイント。日々の流れにうまく組み込めば負担は感じません。
たとえば「ごはん前はお箸を並べる」「寝る前におもちゃを片づける」など、
“時間とセット”で決めると習慣になりやすいです。
子ども家事で生まれる「自分の時間」の活用法
ちょっとしたスキマでリフレッシュ
子どもと家事を分担できるようになると、親にも“数分の余裕”が生まれます。
その時間は、リフレッシュに使うことで心のバランスが整いやすくなります。
「コーヒーを飲む」「スマホを見ない時間を作る」「深呼吸をする」など、
たった5分でも、自分のために使える時間は気持ちを軽くしてくれます。
洗濯を子どもがたたんでいる間に、
ベランダで一息つく。それだけでも効果的です。
副業や趣味にあてるのもおすすめ
少しずつできた“自分時間”は、副業や趣味にも活かせます。
平日の中での5分、10分は積み重なると大きな価値になります。
たとえば、メルカリ出品・ブログ作業・Kindle読書など、
スキマ時間でできる作業をリスト化しておくと効率的です。
「子どもと一緒に掃除」→「空いた10分で出品作業」など、
“時間の流れを設計する”ことも意識してみましょう。
時間を生み出す=心のゆとりも生まれる
ただの“作業時間”ではなく、“心のゆとり”も得られるのが子ども家事の良さです。
焦らず、怒らず、穏やかに過ごせる時間が少しずつ増えていきます。
「忙しい…」という感情が減れば、子どもにも優しくなれますし、
家族の空気も穏やかになります。結果的に、家族全体の幸福度も上がります。
子ども家事は、家庭にとっての“未来への投資”とも言えます。
まとめ|家事は“ひとりで頑張る”ものじゃない
家族で取り組むと家事も楽しくなる
家事を「ひとりで全部やるもの」と考えると、どんどん苦しくなってしまいます。
でも、子どもと一緒に取り組むことで、家事は“共有できる時間”に変わります。
一緒にタオルをたたんだり、掃除をしたり。
手間だと思っていたことが、笑顔のきっかけになることもあります。
子どもも「役に立てた」という満足感を得られるし、
親も負担が減って気持ちに余裕が生まれます。
子育ても家事もチーム戦で考えよう
共働き家庭では、家事も育児も「チーム戦」で乗り切るのがコツです。
誰かひとりが頑張るのではなく、みんなで協力して進めていきましょう。
子どもと一緒に家事をすることで、“チームとしての一体感”も生まれます。
無理なく、笑顔で続けられる関係性をつくることが、
結果的に家庭全体のバランスを整えてくれます。
子どもと一緒にできる家事から、家庭も時間も少しずつ整えていきましょう。
今日からできる小さな一歩が、“自分の時間”と“家族のゆとり”を生み出してくれますよ。
【子どもと一緒にできる工夫】
✅ ながら家事で家事がラクに!時短術5選
✅ 片付く収納テク7選
✅ 家事時短テク完全版はこちら
👉 朝支度をもっとスムーズにするなら