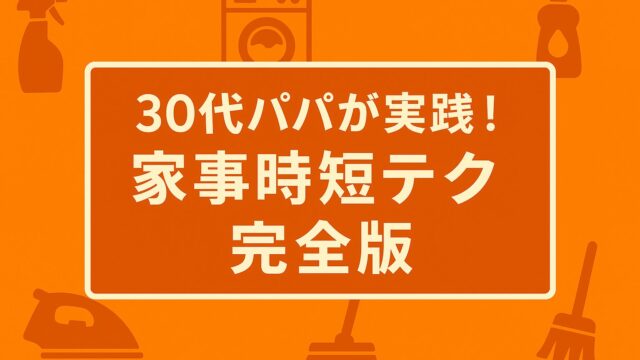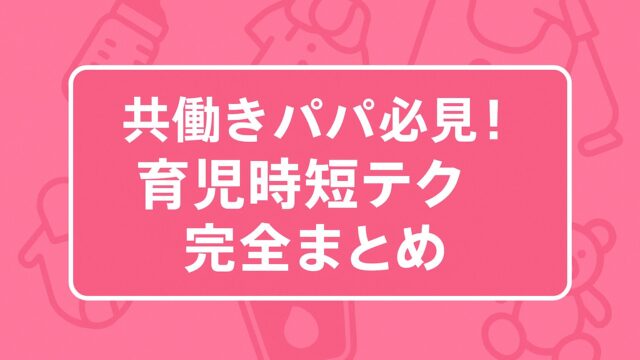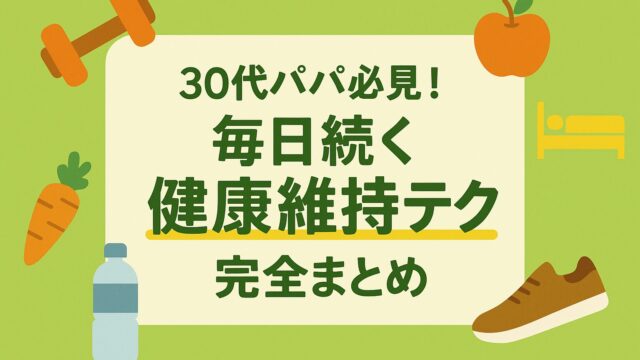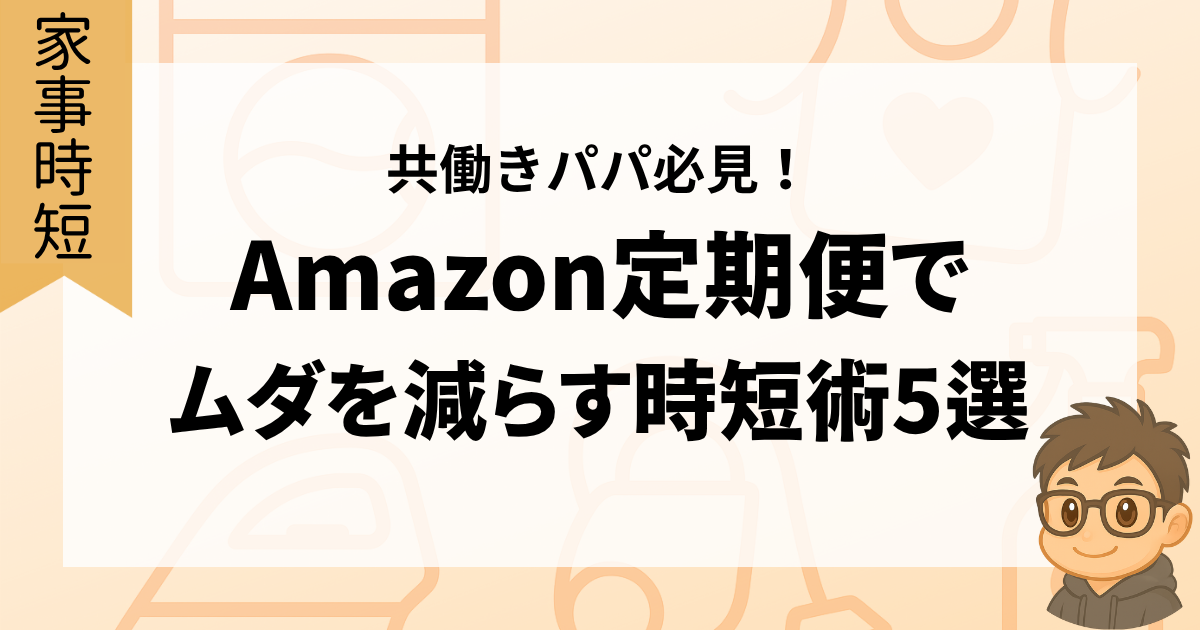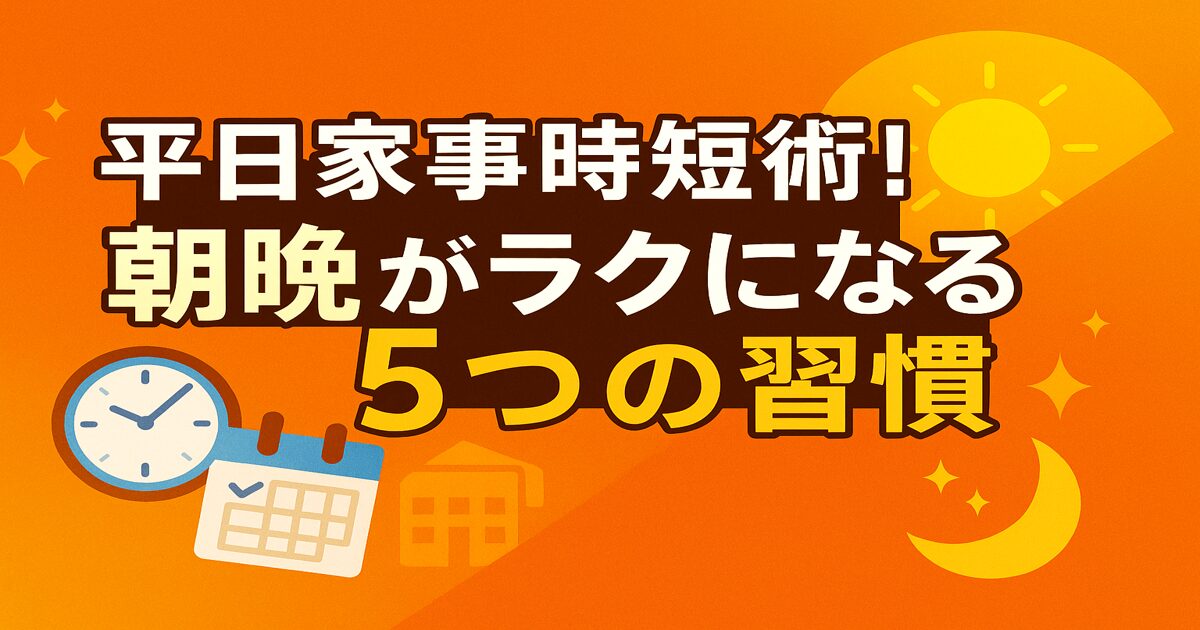共働きパパ必見!片付く収納テク7選

仕事から帰ってきたら、床におもちゃ、机には書類。
「なんでこんなに片付かないんだ…」と
ついため息が出ること、ありませんか?
頑張って収納グッズをそろえても、
気づけばすぐに元通り。
時間も気力も削られる毎日に、もうウンザリしていませんか?
でも実は、片付けやすさは“仕組み”で決まります。
ぼくも、育児と仕事の両立に悩んでいたころ、
「整理しやすい収納」に切り替えたことで、
家の中がぐっとラクになりました。
この記事では、共働きパパでも続けやすい、
“片付けがラクになる収納の工夫7選”を紹介します。
読むことで、「もう散らからない」「片付けが面倒じゃない」
そんな状態に一歩近づけるはずです。
あなたも今日から、片付けのストレスを減らす収納術を
少しずつ取り入れてみませんか?
1. 片付けがラクになる収納の考え方とは
まずは「使いやすさ優先」で考える
「収納=キレイにしまうこと」だと思っていませんか?
でも、実は片付けをラクにするカギは“使いやすさ”にあります。
見た目をそろえるよりも、「出しやすくて、戻しやすい」。
この考え方を持つだけで、片付けにかかる時間はグッと減ります。
たとえば、フタ付きのボックスは見た目は整いますが、
毎回開け閉めが必要だと、戻すのが面倒になりがちです。
すると、気づいたときにはモノが出しっぱなしに…。
収納の役割は“しまうこと”ではなく、戻しやすさを作ること。
特に共働きパパのように、家事時間が限られている場合は、
とにかく「動線」と「手間の少なさ」が最優先です。
無理なく続けられる収納をつくる第一歩として、
“ラクに出せて、サッと戻せる”ことを意識してみましょう。
✅ 収納は“見た目”より“出しやすさ”が大事
・整頓より「戻すのがラク」なことが続けやすさのカギ
・収納用品の選び方も“手間を減らせるか”で考える
・頑張らない工夫こそ、共働き家庭の最適解になる
2. 家の中で散らかりやすい場所は決まっている
よく散らかる“3つのゾーン”に絞って対策
家の中を見回すと、どこもかしこも散らかって見える…。
そんなときは、まず「よく散らかる場所」だけに集中しましょう。
全部を片付けようとすると、時間も気力も足りません。
でも、散らかりやすい場所には“共通のパターン”があります。
たとえばこんな場所です:
・リビングのテーブル周り(郵便物・リモコン・子どもの小物)
・玄関(靴・保育園バッグ)
・テレビ前(おもちゃ・衣類)
こうした場所はモノの出入りが多く、仮置きされやすいので、
最初に収納の仕組みを整えるだけで、全体の印象が大きく変わります。
まずはこの3つの“散らかりゾーン”をピンポイントで改善しましょう。
完璧を目指すより、「ここだけでも整ってる」と思える場所ができると、
家全体の片付けがラクに感じられるようになります。
✅ 集中対策するだけで全体の印象が変わる
・家の中で“散らかりやすい場所”は決まっている
・3か所だけでも整えば、家の印象がグッとラクに
・すべてを片付けようとしないことが、続けるコツ
3. 忙しいパパでも続けやすい!収納テク7選
収納は“がんばるもの”ではなく、“ラクに続けられる仕組み”です。
ここでは、共働きパパでも今日から使える収納アイデアを7つ紹介します。
1. リビングに“なんでもカゴ”を置く
細かいモノをすぐまとめられる「一時置き場」を作ることで、
リビングの散らかりを防げます。
とくに子どものおもちゃや書類に有効です。
✅ カゴひとつでリビングのごちゃつき対策に!
・家族全員がパッと入れられる簡単収納
・時間があるときにまとめて仕分けすればOK
2. 収納場所は「使う場所の近く」に
タオルを洗面所、子どものおもちゃをリビングに。
“使う場所=しまう場所”にするだけで戻す手間が減ります。
✅ 収納場所のズレは“面倒くささ”の元!
・行動動線に合わせて収納を配置し直す
・使ったあとすぐ戻せるから、散らかりにくい
3. 引き出しより“見える収納”を増やす
引き出しの中はキレイに見えても、
しまうのが面倒だと結局出しっぱなしになります。
オープンラックやカゴ収納は、戻しやすさ重視でおすすめです。
✅ 「しまいやすい」からこそ続けられる!
・開け閉め不要で、手間なく戻せる
・子どもも自分で片付けやすい工夫に
4. ラベリングで迷わず戻せるように
どこに戻せばいいか分からないと、人は片付けなくなります。
家族みんなが“見て分かる”収納にするため、
ラベルや名前シールを活用しましょう。
✅ “どこに戻すか”が分かるだけで変わる!
・家族全員が参加できる収納に変わる
・ラベルはイラストでもOK!子どもにも効果的
5. 子どものおもちゃは“種類ごと”に分ける
おもちゃをごちゃ混ぜにすると、片付けも取り出しも面倒に。
ジャンル別にカゴや袋で分けるだけで、格段に片付けやすくなります。
✅ “ザックリ分け”が続けるコツ!
・細かく分類しすぎない方が、逆にうまくいく
・遊んだあとの片付けも時短に
6. ハンガー収納で“畳まない仕組み”を作る
毎日の洗濯物、畳むのが手間なら“ハンガー収納”がおすすめ。
特にシャツや園グッズは、干して→そのままクローゼットが時短のカギ。
✅ “しまう工程”を減らしてラクに!
・たたまない分、ストレスも減る
・収納場所の形に合わせて導線もスムーズに
7. モノを減らす日を1か月に1回作る
収納を工夫しても、モノが多すぎると限界があります。
1か月に1回だけ、“いらないものを手放す日”を設定しましょう。
✅ 収納は「入れる工夫」より「減らす工夫」も大事!
・習慣にすれば、モノが増えにくい家になる
・家族で「手放す」を共有するきっかけにもなる
4. 収納を家族で共有するコツ
「しまう場所が分かる」から片付くようになる
せっかく収納を工夫しても、
自分しか分からない仕組みでは、家族が使いこなせません。
「戻し場所が分からない」→「適当に置く」→「散らかる」
という悪循環が起きてしまいます。
だからこそ、家族みんなが“同じルールで動ける”ことが大切です。
ルールといっても、難しいことではありません。
・モノの定位置を決める(玄関にカギ、テーブルにリモコン など)
・ラベルを貼って“誰が見ても分かる収納”にする
・1〜2か所だけでいいので、家族で共有するスペースを作る
これだけで、「自分だけが片付けてる感覚」はかなり減ります。
家族みんなが片付けに関われる仕組みができれば、
散らかってもすぐリセットできる家になります。
✅ パパだけで頑張らなくてもよくなる仕組みづくり
・片付けのルールを家族と共有すると、負担が減る
・「戻しやすさ」があると、自然と協力が生まれる
・家族にとっても“ラクな収納”を意識するのがポイント
5. 完璧じゃなくてOK。収納は“ラクできること”が正解
大事なのは「片付けのストレスを減らすこと」
SNSや雑誌で見るような“完璧な収納”にあこがれて、
見た目を整えることに時間をかけすぎていませんか?
でも、共働きのパパにとって本当に大事なのは、
見た目の美しさよりも“ラクに続けられる仕組み”です。
たたまなくても、多少ごちゃついていても、
「使いやすくて」「戻しやすい」収納ならOK。
むしろそのほうが、家族みんなが片付けに参加しやすくなります。
片付けに完璧を求めると、いつか無理がきてしまいます。
収納の本当のゴールは「片付けが苦じゃない状態」をつくること。
そのために必要なのは、ラクを許す考え方です。
あなた自身が“ラクできる工夫”を選びながら、
無理なく続けられる収納スタイルを見つけていきましょう。
✅ 無理しない収納が“ちょうどいい暮らし”を作る
・完璧じゃなくても、暮らしは回る
・ストレスが減れば、家族の時間も増える
・「ラクでいい」が、結果的に一番続くコツ
まとめ|パパでもできる!ラクに片付く家づくりへ
片付けが苦手でも、時間がなくても、
収納を少し工夫するだけで、日々の家事はぐっとラクになります。
特別なテクニックや高い収納グッズはいりません。
必要なのは、「無理しなくていい」「続けられる仕組み」です。
今日紹介した収納テクをひとつでも試してみてください。
片付けのストレスが減ると、家での過ごし方も変わります。
あなたの家が、もっと心地よくなる第一歩になりますように。
【関連記事はこちら】
✅ 洗濯がラクになる!導線づくりの時短テク5選
✅ 家事がラクになる!子育て家庭時短家電TOP3
✅ 家事時短テク完全版はこちら
👉 育児もラクにしたい方はこちら